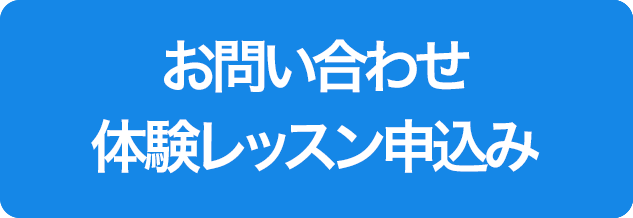奈良市ジュニアアスリート専門ジムでスポーツ傷害を専門で行うトレーニングジムのasukaトレーニングクラブ。
小学生の高学年~中学生のスポーツをしているお子様に多いスポーツ傷害として今日から
3回に分けてその症状を改善する方法をお届けいたします。
小学生~中学生に多いスポーツ傷害では
シーバー、オスグッド、グロインペイン症候群、有痛性外頸骨があげられます。
腰には分離症やヘルニアがありますが、これらは姿勢にも関係することですね。
今日から3回に分けて上記の中からのスポーツ傷害からいかに競技に復帰するかをお届けしていきます。
今日はシーバー病。
シーバー病とは別名踵骨骨端症と呼ばれています、かかとの成長軟骨に様々な動作により負担がかかり
おこる炎症。になります。
基本治す方法は現在では確立されていません。ほとんが湿布、テープなどを張る、安静にするなどの保存的治療が
主になると思います。しかし、競技を行う上でいつまで保存するのか1カ月、3カ月、6カ月?これが
わからないのです。成長期のスポーツ傷害は成長している過程で起きるためにどの程度安静にすればいいのかがわからないのが
現状です。
ではシーバーを改善して元気に走るにはどのようにすればいいのか。
まず、スポーツ傷害よ呼ばれる傷害には原因が必ずあるのです、長年多くのスポーツ選手をグラウンド、体育館の現場で
診てきて治療をしてきた結果です。
スポーツ傷害は1日でおこるわけではありません、繰り返し同じ不自然な動作が引き起こすのです。
シーバー病では私が治療を行う選手の特徴として、走る時や止まる時に爪先から地面に接地している選手が
ほとんどです。
このつま先接地が踵に大きな負担をかけるのです。
走る時でも止まる時でもつま先で接地すると
足首は底屈と呼ばれる動作になります。この時アキレス腱は収縮されているのですが、
次の瞬間踵が地面につくと大きな力でアキレス腱が引き伸ばされることになります。
この強い引き伸ばしと収縮が繰り返すことでアキレス腱の付着である踵に痛みを発症することになります。
改善するにはまず運動するときや歩行の時の動作から改善していきましょう。

①足裏の位置

②地面に対して足裏の方向
地面に対しては足首は背屈の状態で地面に接地することで過度な負担を踵にかけることはなくします。
また走る動作では時速10キロ以上になった状態から急激にブレーキをかけるとどうしてもつま先で接地をすると
地面からの力は真下方向ではなく前方→後方に対する力になり身体で吸収する部分が無くなります。
その結果踵への底背屈で吸収を行う為踵への負担が増大します。
これが成長期に行われることで軟骨への刺激を増し痛みになると推測されます。
その為、湿布や安静は一時的な処置になるため、出来るだけ早い時期から動作改善を行いましょう。
安静にしても一時的なため、また同じような動作で痛みをぶり返すことになります。
爪先接地を中止し足裏全体で地面を押す感覚のトレーニングが必要です。
まずは
①歩行での歩き方
②歩行から止まる時に爪先での接地を改善
⓷走る時もつま先で接地しない
④走って止まるときに爪先で接地しない
この4つを段階的に行いましょう。
動作が変われば動かしていた所もかわりシーバー病を完治することも可能です。
痛みの原因はほとんどが動作のエラーからおきます。その為正しい動作で動くことで
痛みは改善することになります。
動作を変えてみることで競技スポーツは大きく変化します。
トレーナー兼コーチ
野島
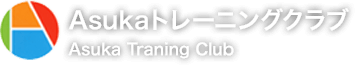
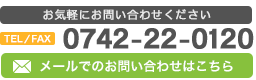
![月~水・金 8:00~12:00 [最終受付 11:45] 月~金 16:00~21:30 ※水曜日のみ 17:00~ [最終受付 20:45 ] 土・祝 8:00~13:00 [最終受付 12:30]](/img/reception.png)

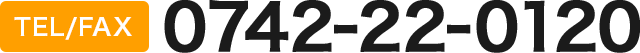
![月~水・金 8:00~12:00 [最終受付 11:45] 月~金 16:00~21:30 ※水曜日のみ 17:00~ [最終受付 20:45 ] 土・祝 8:00~13:00 [最終受付 12:30]](/img/common/h_time.png)

 この記事を書いた人
この記事を書いた人